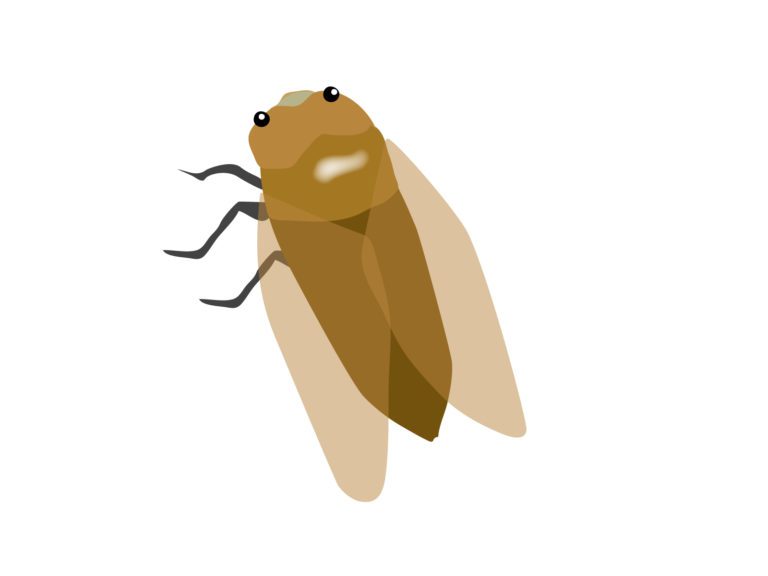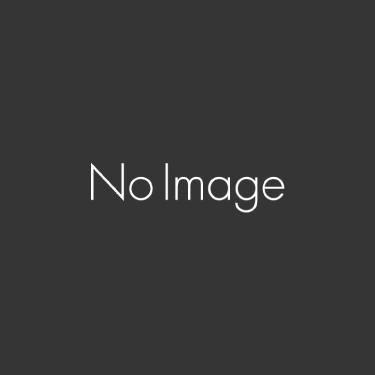【もう一つのウソ】
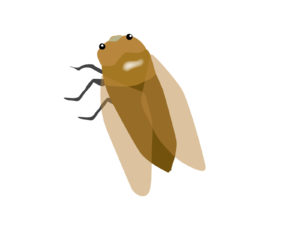
「じゃあ、本当にこれで最後ね。これが理解できたら、コトちゃん基礎講座の卒業証書を授与いたしま~す。コトちゃんも、そろそろバイトに行かなきゃならない時間だからね~。」とコトハはまた、ふざけて言う。
「バイト?」
「うん、ちょっと前から始めたの。」
「ふーん。」と僕が頷き終わる前に、コトハがまた話し始めた。
「さっき、ケアレスウィスパーはお兄ちゃんに二つのウソを信じこませるって言ったわよね。一つ目が『お兄ちゃんに価値がない。』っていうウソ。
もう一つは何だと思う?」
「そんなもん、分かるわけねえって言ってんじゃん。」と答えながら、僕はアイスコーヒーを口にした。
「それはね。
『お兄ちゃんに、愛がない』っていうウソよ。
ケアレスウィスパーは『お兄ちゃんは愛がない。』というウソをお兄ちゃんに信じこませようとするの。」
「確かにオレには愛がない。」と僕は、開き直るようにブツブツ言った。
するとコトハが、また強い声を出した。
「だから~!
それが、お兄ちゃんがケアレスウィスパーの言いなりになってるって、さっきから言ってんじゃないのぉ~!
もおおお!
お兄ちゃん、しっかりしなちゃいっ!」と言って、また僕の頭を叩く。
僕は叩かれながら、アイスコーヒーをゴクリと飲み込んだ。アイスコーヒーがやけに冷たい。僕の頭を冷やすために、コトハはアイスコーヒーをキンキンに冷やしてきたみたいだ。
「お兄ちゃんは本当にしょうがないねえ。」と言って、話を続けるコトハの表情が、少し神妙になった。
「これからの話は、すぐには理解できないと思う。
でも、お兄ちゃんの心の中にいる、普通で当たり前で本当のお兄ちゃんに、お兄ちゃんから直接、話しかけてもらいたいの。
わかった?」
僕は返事をする代わりに、もう一度アイスコーヒーをゴクリと鳴らして飲み込んだ。
やはり、やけに冷たい。
そのゴクリという音を僕の頷きと解釈したコトハは話を続けた。
「実はね。
お兄ちゃんはユリさんのためにダメダメ人間になったの。
お兄ちゃんは、ユリさんのために、仕事でヘマをしてクビになったの。
ユリさんに『完璧でなくても大丈夫。ほら、ボクを見て。十分、幸せに生きていけるでしょ。』という具合に。」
「はあ~。オレはオレで、勉強だって部活だって仕事だって、一生懸命やったんだぜ。わざとヘマやったり、ユリちゃんみたいにわざとテストで悪い点数を取った訳じゃないぜ。」と、僕は、さすがに、反論した。
「だから、いいの!
もしお兄ちゃんが、勉強や仕事をサボってたならユリさんは変わらなかったの。
ユリさんはお兄ちゃんを見ながら、こう思った。
『一生懸命やっても、うまくできない人もいるんだな。でも、そうやって失敗しながらも色々なことにチャレンジするノリくんって好きだな。上手じゃないけど、ノリくんの弾き語りは、心を打つし。』って。」
「『オレの弾き語りが上手じゃない』っていうのは、余計じゃねえ?おれの弾き語りはみんなにも評判が良かったんだかんな。」と、僕はブツブツいじけるように反論した。
もちろん、コトハは僕の話など聴く気はないという風に、相変わらず静かに力強く話を続ける。
「ユリさんに『結果に振り回されず、好きなことを一生懸命やる生きかたっていいな。』って思わせる必要があったの。」
僕はコトハの話が理解できず、コトハに馬鹿にされているみたいで、あまり気分が良くなかった。が、コトハが「バイトがある」と言っていたので、そのまま話を聴いた。
コトハは続ける。
「お兄ちゃんと付き合うようになってから、ユリさんはこう思うようになった。
『私も、成績や収入や結果や世間体ばかり気にするのをやめて、自由に自分の好きなことをやってみよう』って。
だから、ユリさんは中学の時に苦手な楽器に挑戦した。頭の良い進学高校に行くのも辞めた。4年制大学に行かず短大に行って、保育士の免許を取って一番大好きなピアノ教室を開いた。
もちろん、ご両親は反対した。『何で一流の大学や一流の企業に行かないんだ?何で、ピアノ教室なんだ?』と言って。
でも、ユリさんはお兄ちゃんから学んだの。『ダメだったら、またその時に考えればいいや』って。『とにかく、今、やりたいことを精一杯やって、後悔しないようにしよう。』って。一流大学に行って一流企業に入って、完璧に生きることが幸せなんじゃないということを、お兄ちゃんは身をもって示した。
ユリさんは、それを肌で感じた。お兄ちゃんはダメダメ人間になって、人に馬鹿にされたとしても、純粋にやりたいことをやって生きる素晴らしさをユリさんに教えてあげた。
お兄ちゃんはそうやって、まさにカラダを張ってユリさんを愛していたの。
お兄ちゃんと付き合うまでは、ユリさんにはそんな生き方を選択する勇気も決断力もなかった。ただ、ご両親や先生の言うことに、完璧に従う人生を生きていた。
もし、お兄ちゃんに出会わなかったら、ユリさんは一流企業に就職し、完璧に仕事をこなすキャリアウーマンになっていた。そして、常に自分に完璧を課しながら生きなければならなかった。それが、ユリさんの宿命のようなものだった。
でも、ユリさんのように繊細で控えめな女性にとって、そういう人生はとても耐えられるようなものではなかった。もしかしたら、ユリさんは自殺することになっていたのかもしれない。
でも、そこに、お兄ちゃんが現れた。お兄ちゃんは、ユリさんの生きている世界にはいない完璧とはほど遠い人だった。
例えるなら、お兄ちゃんはジャスミン王女の前に現れたアラジンのようだった。お兄ちゃんはアラジンみたいにイケメンでもなかったし、魔法のジュータンに乗せてあげることもできなかった。
だけど、ユリさんを自殺から救うくらいの素晴らしい役割を果たしたっていうことなの。
それは、お兄ちゃんがコトちゃんを普通に当たり前にいじめから助けてくれたのと一緒。つまり、お兄ちゃんは無意識に普通に当たり前にユリさんを自殺から救っていたの。
それが、お兄ちゃんの愛情なの!
お兄ちゃんは、そういう愛情をユリさんに注いで生きて来たの!」
セミは、相変わらず、元気に鳴いている。
ミーン、ミー、ミー、ミー、ミー…。