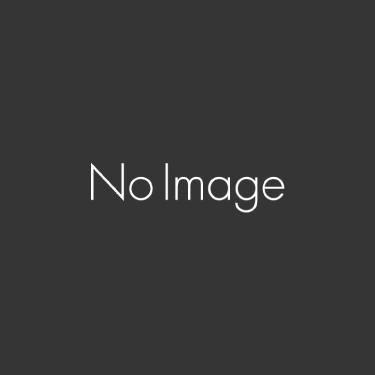【声がちがう】

「僕に、愛があった…。僕に、価値があった…。
コトハの言う通りなのかもしれない…。」
僕の体からは、全てのチカラが抜けていた。
「そろそろ準備してロトールに行かなきゃ。」
そう思いながらも、僕の頭は空っぽになっている。放心状態になっている。体もフラフラしている。
僕はノソノソと浴室に入り、コーヒーのついたティーシャツと半ズボンを脱ぎシャワーを浴びた。
しかし、立っているのも辛く、ただ体育座りになって膝を抱えて座り、冷水のシャワーを頭から浴びた。
僕はしゃがみこんだまま、頭から冷水を浴び続けた。
「過去のことは、もう、ぜんぶ、終わってしまった。」
そんな不思議な感覚に陥っていた。
頭の中も心の中も、空っぽになっている。
何も考えられない。
心に湧いてくるものもない。
僕は真空状態になっている。
アイスコーヒーのようにキンキンに体が冷えたところで、僕は浴室から僕の体を出し、僕の体に、新しいティーシャツと新しいズボンをはかせて、僕はフラフラ家を出た。
やはりまだ、体からチカラが抜けたままだ。
ロトールまでは、バスで行けば5分で着く。でも、歩いて行きたくなった。
ただあてもなく、歩きたい気分だった。もし道を間違えてロトールに着かなくても、別に構わない。そう思いながら僕はゆっくり歩いた。
月がきれいだ。
風が心地いい。
遠くでカエルがゲロゲロ楽しそうに鳴いている。
風鈴の音も涼しさを演出してくれている。
一番星が見える。
七夕の笹の木に短冊が飾ってあった。
その中の一枚を、手の平でそっとすくって読んだ。
「世界中に愛が満ち溢れますように。」
すべてが気持ちいい。
世界はこんなにも愛であふれていたのか?
何で気づかなかったのだろう?
何で愛があふれていることを感じられなかったのだろうか?
フラフラと千鳥足で歩きながら漂流していたら、たまたまロトールというコーヒーショップに辿り着いたかのようにして、僕はロトールの入り口の前に立った。
懐かしい。
扉を開けると、いつもユリが「いらっしゃいませ!」と言ってくれた。
ユリの声が聴こえただけで、僕は胸のときめきを感じた。
そんな過去を思い出しながら、僕は店の扉を開けた。
「いらっしゃいませ!」
コトハの声だ。コトハは、本当にバイトを始めていたんだ。引きこもっていたコトハがバイトをしているという信じがたい光景を、僕は自分の目で見て確認した。
「お兄ちゃん、遅かったじゃない!来ないんじゃないかって、心配してたのよ。奥の席、空いてるからどうぞ。」と、コトハが元気な声で、僕を迎え入れた。
「このコトハが、昨日まで、(家では)引きこもっていたなんて…。」と思いながら、僕は奥の席へと向かった。
マスターが通りすがりに声をかけてくる。「コトちゃんには世話になってるよ。明るくて、お客様にも好評だよ。ありがとな。」
僕は、席に座った。信じにくい不思議な光景を見た僕は、現実を疑いたくなった。ほっぺたをつまんでみた。しかしやはり、それは現実だった。
程なく食事が運ばれてきた。
「お待たせいたしました。」
僕は、「注文してないんだけど…。」
「あー。今日は、コトハのおごりだった。」
と、自分の心の中で、一人二役の会話をした。
目の前に運ばれてきた料理は、僕の大好物「ウィンナーペペロンチーノ」だ!
「ガーリックとペッパーの効いたペペロンチーノ。さらに、辛口のウィンナーを、ユリが僕のためだけに特別にのせてくれた。ビールを飲みながら食べると、夏の暑さも仕事の疲れも吹き飛んだんだよな。
でも今日はユリちゃんがいないから、その効果は半分以下か…。」と一人でブツブツ考えていた時、
ウィンナーペペロンチーノを運んできた女性の声が、コトハの声と少し違う気がした。
僕は顔を上げた。
「ユリちゃ…?!」
僕の心臓が、また、止まった。