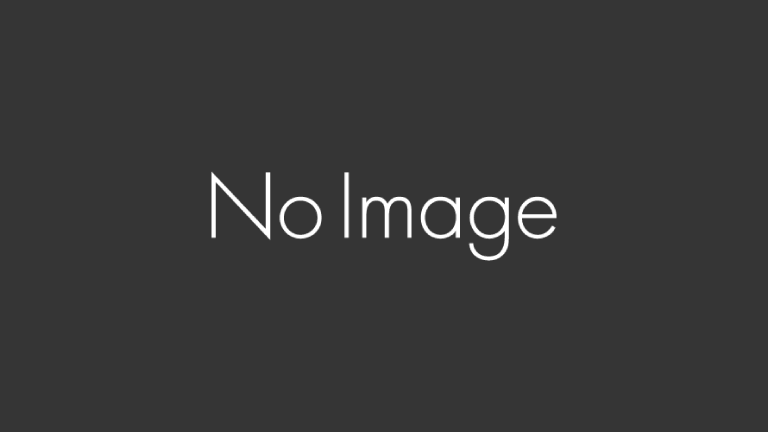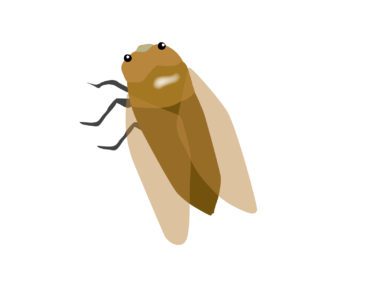【おまえの兄ちゃんヨダレこぼしてたな】
「お兄ちゃんは、無意識に、普通に当たり前に、ユリさんを自殺から救っていた。お兄ちゃんは、そういう愛情をユリさんに注いで生きて来たの!」とコトハは、言った。
僕にはよく理解できなかったが、 コトハが僕のために本気で一生懸命話してくれていることだけは伝わってきた。
そして単純に、そのことが嬉しかった。
コトハは一呼吸置いてから、静かに言った。
「そろそろコトちゃん、ロトールに行かなきゃならないからよく復習しておいてね。」
「ロトール…?
バイトって、ロトールでバイトしてるってことか?」と、ユリが働いているロトールでコトハがバイトしていると聴いた僕は、ビックリして言った。
コトハは、涼しげに応える。
「そうよ。午後8時頃には、ロトールで夜ごはんを用意して待ってる。今日はお父さんもお母さんも、旅行に行っていないでしょ。だから、今日はコトちゃんが、お兄ちゃんにご馳走してあげる。
ユリさんはいないから大丈夫。2週間前、ピアノの先生に専念するってロトールを辞めちゃったから。
もう時間がないから行くね。
ちゃんとティーシャツくらいは着替えて来てよ。
『お前の兄ちゃん、ヨダレこぼしてたな。』なんて言われたくないから。じゃあね。」
コトハは、言いたいことを言いたいだけ言って出て行った。
相変わらず、セミは元気に鳴いているが、僕の気持ちはやけに静かだった。
僕はキンキンに冷えたアイスコーヒーを飲み切り、コトハの言葉をボーっと思い返した。
「僕がユリを救うため、わざとダメダメ人間になった?」
「それが僕のユリへの愛情だった?」
「そんなこと信じられない。」
「何でも完璧にこなすユリには、僕のようなダメダメ人間が必要だった?」
「だから僕は、高校の頃からダメダメ人間になった?」
「僕はユリのために、会社もクビになった?」
「『完璧でなくても、十分、幸せに生きていけるんだよ。ほら僕を見てごらん。』とユリに伝えるために?」
「僕は自分のカラダを張って、ユリを救った?」
「僕がコトハをいじめから守ったように?」
「僕はユリに対しても、無意識にそういう愛情を注いでいた?」
「僕に愛がある?」
「僕に価値がある?」
「そんなこと信じられない。」
が、なぜか、僕の目から涙が溢れてくる。
「僕に、愛がある?」
「僕に、価値がある?」
そう自分に問いかけると、なぜか涙が込み上げてきて、涙が止まらない。この涙は、なんなんだ!?
何で、僕は、泣いているんだ!?
何で、涙が込み上げてくるんだ!?
僕は、自分の体を張って、ユリを愛した?
僕には、そんな愛があった?
僕は、そうやって、ユリを愛してきた?
「そんな!」
「信じられない!」
でも、涙が止まらない!
僕は、嗚咽している!
喉を締め付けられるようにして泣いている。
ユリの愛情を感じたからではない。
「僕に愛があった?
僕に価値があった?」
そう自分に問いかけると、涙があふれてとまらない。鼻水も止まらない。
僕は、どうなっているんだ?
コトハは、言った。
「信じられないと思う。とにかく、お兄ちゃんの中の当たり前で普通のお兄ちゃんに問いかけてみて。」と。
「僕はユリを愛していた?僕の中に愛があった?
僕の中の罪悪感が、『僕には愛がない』というウソを僕に信じ込ませていた?
そして僕は、そのケアレスウィスパーの言葉を信じ、僕には愛がないと思い込んでしまっていた?
ユリの言葉が脳裏をよぎる。
「ノリくん、すごいよ。何でそんなに頑張れるの?私はただ、できることをやっているだけ。でもノリくんは違う。できないことに挑戦する。
不器用だけど、そんな純粋なノリくんが好きだな。」
なぜ、僕は、ユリの言葉を素直に受け容れなかったんだ!
なぜ、ユリの言葉を信じなかったんだ!
きっと、ユリは本気でそう言っていた!
なぜ、僕はユリを信じないで、ケアレスウィスパーのウソを信じてしまったんだ!
僕に愛があった!
僕に価値があった!
ユリに愛があった!
それなのに、僕は…。
僕はひたすら泣き続けた。
気がついたら、もう夜の7時を回っていた。
あたりは暗くなっている。
僕は1時間以上、泣き続けていた。